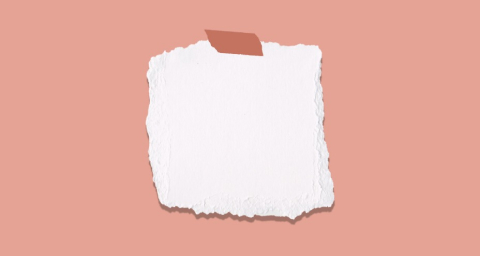SNS上の誹謗中傷は、社会全体で取り組むべき重要な課題となっており、スポーツ界においても深刻化しています。
2024年夏に開催されたパリオリンピックでは、世界中の注目を集める中、多くの感動が生まれた一方で、一部の選手に対してSNS上で誹謗中傷や心無いコメントが投稿される事例が相次ぎ、改めて社会的な問題として浮き彫りになりました。
特に注目を集めた競技のひとつがバレーボールでした。
プレーに対する批判を超え、SNSで差別的な発言や個人攻撃といった投稿が多数見受けられました。
また、SNS上の投稿にとどまらず、選手のSNSアカウント宛にダイレクトメッセージ(DM)で届くこともあったと明かされています。
不適切な発言や過剰な批判により深く傷ついたのは、選手本人であることは言うまでもありませんが、応援していたファンや視聴者の中にも、心を痛めた方は少なからずいたと考えられます。
なお、パリオリンピック後、日本バレーボール協会(JVA)から法的措置の検討や外部専門家との連携といった具体的な対処方針が公式に示されることはありませんでした。このため、2025年6月~7月に開催された国際大会「バレーボールネーションズリーグ(VNL)」においても、同様の誹謗中傷が再発するのではないかという懸念がありました。しかし現時点では、VNLに関連する深刻な中傷や炎上が発生したという報告は確認されていません。
この違いは、何に起因しているのでしょうか。
誹謗中傷の傾向
SNSにおける誹謗中傷は、競技の規模や視聴者層によって投稿傾向に違いが見られます。
| 状況 | 投稿傾向 |
| 普段のリーグ戦・小規模大会 | コアファンが中心。比較的穏やかで建設的な意見が多い。 |
| オリンピック・W杯など大規模国際大会 | ライト層・一時的ファン(にわか層)が急増。誹謗中傷が急激に増える。 |
特に、判定ミスや敗戦などをきっかけに、SNS上には批判的・感情的なコメントが急増し、炎上に発展するケースも見られます。
国際大会「バレーボールネーションズリーグ(VNL)」は、男女18チームずつが参加する規模の大きな大会ではあるものの、毎年開催されていることに加え、テレビ放送において地上波で放映されたのは予選の日本ラウンドのみでした。他国での予選やファイナルラウンドは、主にBS放送や配信サービスを通じて視聴されていたため、視聴者の多くは熱心なコアファン層であったことが推測されます。
こうした点から、VNLは「普段のリーグ戦や小規模大会」と同様の状況に近く、SNS上での誹謗中傷も比較的少なかった可能性があります。
参考:
“アスリート 心のSOS” トップ選手に何が?「五輪で増幅 SNSひぼう中傷 徹底分析で見えた"俺理論"」
(NHK「クローズアップ現代」)
勝てば「日本万歳」、負けると「戦犯叩き」…W杯で「にわかサッカーファン」が大量発生するメカニズム
(PRESIDENT Online)
ライト層・一時的ファン(にわか層)が誹謗中傷に加担しやすい理由
それでは、ライト層・一時的ファン(にわか層)がSNS上で誹謗中傷を投稿してしまうのは何故なのでしょうか。
以下の様な要因が考えられます。
| 要因 | 解説 |
|
過剰な期待や理想の押し付け |
知識不足により根拠のない期待をしすぎて、負けたときに強く失望 |
|
知識不足による感情の揺れ |
試合結果や選手のミスといった表面的な事象で判断しがち。知識による裏付けがない分、感情に左右されやすい傾向がある。勝利すれば熱狂的に喜び、敗北すれば失望し感情的な批判を繰り返す。 |
|
確証バイアス |
自分にとって都合のよい情報ばかりを集める傾向。一部のミスや情報に過剰に反応し、他の情報を無視して攻撃を正当化する。 |
|
群衆心理 |
他人が攻撃している様子を見て「自分もやっていい」と思ってしまう。群れの中では責任感や理性が薄れがち(匿名性)で、感情が伝染しやすく過激な行動にも発展しやすい。 |
特に「群衆心理」は、ファン層に関係なく誰にでも起こりうる心理状態ですが、スポーツに関する知識や理解が乏しい場合には、こうした心理がより強く作用し、誹謗中傷に加担しやすくなってしまうのではないかと思われます。
これらの要因を正しく理解することは、SNS上の誹謗中傷を根本的に減らすための重要な第一歩です。
あわせて、SNS上の誹謗中傷の全体像や社会的な影響については、以下の記事でも解説しています。
スポーツ界におけるSNS時代の誹謗中傷問題とその対応:現状と今後の展望
続いては、この問題にどう対処していくべきか、具体的な対策を見ていきましょう。
分野別に見る誹謗中傷対策
誹謗中傷への対応は、一つの手段に頼るのではなく、複数の分野で並行して進める多角的な取り組みが求められます。主な対策を以下の表にまとめました。
| 分野 | 対応策 |
|
教育 |
ファンに向けたリテラシー教育(中傷の法的リスク、応援のあり方) |
|
プラットフォーム運営側 |
通報機能強化、AIによる投稿フィルタリング、警告表示など |
|
スポーツ組織 |
中傷対応の体制整備(削除要請、弁護士連携、相談窓口) |
|
選手個人 |
SNSの運用方針の見直し(通知オフ設定、コメント制限など) |
このように、誹謗中傷を減らすためには、ひとつの対策に頼るのではなく、様々な視点から継続的に取り組むことが重要です。関係者それぞれが課題を認識し、適切な対策を講じることが、選手とファンの双方にとって安心してスポーツを楽しめる環境づくりに繋がります。
こうした多角的な対策が不可欠である一方で、ファンとして心に留めておきたい、スポーツ観戦のあるべき姿についても考えてみましょう。
スポーツ観戦のあるべき姿とは
スポーツ観戦の楽しみ方は、価値観や社会的な背景によって人それぞれ異なります。しかし、どんな楽しみ方であっても、選手やチーム、そしてスポーツそのものへのリスペクトを土台とすることが大切です。
勝敗によって大きく感情を動かされるのはスポーツ観戦の醍醐味ですが、それだけがすべてではありません。
試合の勝敗だけでなく、選手が積み重ねてきた努力や、その背景にあるストーリーにも目を向けることが大切です。「勝てば賞賛、負ければバッシング」ではなく、選手の健闘をたたえる姿勢こそが観戦者に求められるマナーといえます。
みんなでフェアプレー精神を共有することで、誰もが気持ちよくスポーツを楽しめる環境が生まれるのです。
応援のスタイルは、批判や罵倒ではなく「どうすればもっと良くなるか」という前向きな視点を持つことが大切です。拍手や応援歌に加えて、ミスの後に送られる励ましの拍手や、スタジアムでの一体感あるコール、さらにはSNS上での建設的な発信など、選手の背中を押す応援のかたちはさまざまです。
バレーボール日本代表の髙橋藍選手も、誹謗中傷に対して「もちろん選手はファンの方々がいてやれていると思っている。できればその言葉は、選手を褒める形で使ってほしい部分がある」(出典:スポニチ Sponichi Annex)と述べています。
いま改めて、SNSには建設的で前向きなやり取りが求められているといえるでしょう。
まとめ
SNSの普及によって、アスリートとファンの距離はかつてないほど近くなりました。その一方で、無責任な投稿や過激な言葉が選手を傷つけ、スポーツが持つ本来の精神や魅力、楽しむ姿勢を損なう要因となっています。
誹謗中傷を減らし、健全な応援文化を育てていくためには、私たち一人ひとりのリテラシーと意識が不可欠です。
アディッシュでは、企業や個人のSNSアカウント・Webサイトなどを24時間365日体制で監視し、誹謗中傷や炎上につながる投稿を早期に発見・報告するサービスを提供しています。
万が一、投稿の削除依頼など法的対応が必要な状況となった場合には、提携している弁護士をご紹介することも可能です。
さらに、リスクを未然に防ぐため、企業の従業員を対象としたSNS研修サービスも提供しています。SNSのリテラシー向上や炎上リスク対策を学ぶことで、SNS活用における意識を高め、より安全な情報発信をサポートします。