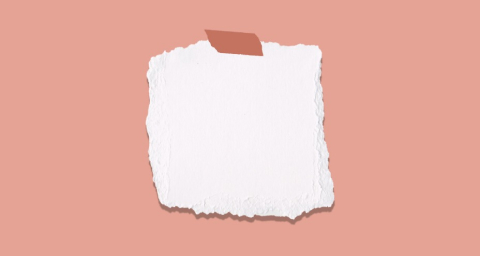なぜ誘導をしようとするのか
ネット掲示板などのコミュニティに利用者がURLを書き込む理由は何でしょうか?
他のユーザーを誘導する経路を作る背景には下記のような意図があると考えられます。
-
善意の情報提供として
自身にとってメリットの薄い情報提供としてのURL記載。
例えば「スイーツ好きコミュニティ」にオススメしたいケーキ屋のウェブサイトのURLを書き込むなど。 -
コミュニケーションの場を移す意図
他のコミュニティに移って交流を続けるケース。例えば今のコミュニティに制限が多く、親密なコミュニケーションができないなどの不満により発生しやすい。
「出会い」を目的として、個人情報を書き込むことが可能なフォーム設置ページへ誘導することもある。 -
商用的利用を意図した誘導
自身の利益に直結するようなウェブサイトへの誘導。例えば自分が経営する店舗サイトへの誘導など。悪意を持って、害のあるリンク先へ誘導することも考えられ得る。
コミュニティのコンセプトに基づく「情報の共有」であれば、許容するサイト運営者もいるかもしれません。
一方で、ユーザーの離脱を招くような他コミュニティへの誘導や悪意のある誘導は厳しく制限をしたいという方針も考えられます。
URL以外の注意すべき誘導
投稿の監視において、URLにのみ注目してしまうと、別の形での誘導を見落とす可能性があります。
例えば、FacebookのようなSNSにおいては個別ユーザーのプロフィールページがウェブサイトのようなものだと考えられます。書き込み内にURLの記載がなくとも、書き込んだユーザーのプロフィールページに遷移できる仕組みになっていれば、誘導の経路となるでしょう。
具体的には「皆様にとって役立つ情報を提供しています。ぜひプロフィールページを見に来てください!」などの書き込みが想定されます。
また、URLの代替手段としてQRコードなどの画像を貼り付けるケースもあります。今後も誘導のための手段としては様々な形式が出現すると考えられ、情報のキャッチアップも求められています。
投稿監視で早期対応を
そもそもURL自体を書き込めないようにサイトを設計してしまうこともできます。
ただし、前述のようにURL以外で誘導するような様々な手段があることから、監視によって対策していくことが望ましいでしょう。
また、事前監視によってサイト掲載前にチェックする方法もあります。事前監視についてはユーザーのコミュニケーションのリアルタイム性が損なわれることから、サイトコンセプトを踏まえた上で検討すべきです。
いずれにせよ利用者にとって心地の良いコミュニティであり、運営者にとってビジネスを成立させやすいコミュニティの実現において、投稿監視の重要度は高いと言えるでしょう。
adishでは、投稿監視サービスによりインターネットコミュニティの健全化を支援する「コミュニティ監視」を提供しております。お気軽にお問い合わせください。