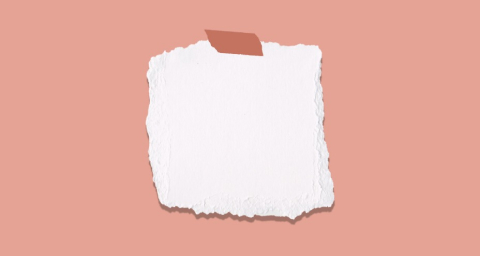ゲーム業界が見逃しがちな「炎上リスク」実はすぐそばに
近年、スマートフォン、家庭用ゲーム機、PC等プラットフォームを問わずインフルエンサーを起用したゲーム配信のプロモーションが加速しています。YouTubeやTikTokなどの動画プラットフォームでは、フォロワー数が数万人〜数百万人の配信者がゲーム実況を行うと、そのインパクトは広告費数千万円分に匹敵すると言われています。
ユーザーは企業発信の広告よりも、自分に近い視点を持つ配信者のリアルな言葉に強く反応します。特にゲーム分野では「実際に遊んでいる人の率直な感想」や「生配信でのリアクション」が、タイトルへの信頼や購買意欲を左右する重要な情報源になりつつあります。
たとえば、あるスマホRPGタイトルでは、人気実況者を複数起用した動画施策によって、前月比でダウンロード数が2倍近くに伸びたという報告があります。また、スマホゲーム実況市場全体では動画再生が年間10億回を超えるとの調査もあり、ユーザーの関心を高め、共感を得るための有効な手段とされています。
本記事では、ゲーム業界におけるインフルエンサー施策のリスクと対策について、事例を交えながら解説します。
炎上リスクの実態と事例
炎上はどの企業にも起こり得るリスクです。ここでは、実際に発生した配信での炎上事例を紹介し、どのような行動や背景が問題視されたのかを見ていきます。
- プロゲーマーの差別的発言
あるプロゲーマーが配信中に差別的と受け取られる発言を行い、所属チームは謝罪文を公表したものの、最終的には選手契約解除となりました。また、スポンサー企業も選手紹介ページを削除し、契約を打ち切る対応を取りました。 - チートツールで書類送検
チートツールを使用した少年3名が、電子計算機損壊等業務妨害容疑で書類送検されました。ゲームに意図しない動作を繰り返し起こさせることで、運営会社に業務に支障を与えたとされます。 - モラルが問われた炎上
ある配信者が、購入したゲームが面白くない等の理由で、配信中に返金請求を繰り返しました。
「ルールを悪用している」「リスペクトが欠けている」との指摘が相次ぎ、業界内外でモラルが問われる騒動となりました。
リスクが生まれる背景
炎上は突然起きるように見えて、実はその背景にはいくつかの共通する要因があります。ここでは、企業と配信者の間に生じがちなズレや、配信の特性がもたらすリスクをひもといていきます。
- 「企業の顔」という意識の欠如
視聴者数・登録者数=影響力とはいえ、企業タイアップ時は、「企業公式の一部」として配信を行う必要があります。しかし、自身の発言が、結果的に企業イメージを傷つけてしまうリスクを認識しきれていないケースがあります。 - 準備不足のまま飛び込む
SNSマーケティングはトレンドの移り変わりが速く、競合他社の事例を追いかけるうちに準備不足の状態で配信をスタートしてしまうケースもあります。トレンドを追うことは重要ですが、その前に十分な事前の炎上のリスク確認を設けないと、想定外のトラブルを招きます。
- ライブ配信の即時性
収録動画の場合は編集でカットができますが、生放送は一発勝負です。その場のノリや勢いで発せられた言葉が発信され、そのままアーカイブとして残り続けます。問題発言への対策として、リアルタイムでの配信監視、配信内容チェックの強化、配信者への事前教育・ルール共有といった対策が重要です。
炎上を防ぐ、3つの対策
炎上リスクは「誰にでも起こり得ること」ですが、だからといって運任せにしていては、企業やブランドの信頼を守ることはできません。ここでは、炎上を未然に防ぐために、実施すべき対策を3つのフェーズに分けてご紹介します。
1. 起用前のリスク評価
インフルエンサーを起用する前に、リスクの有無を見極めるフェーズです。
- SNS・動画履歴の事前調査
過去のSNS投稿や配信内容に問題のある発言・行動がないか、専門スタッフによる目視で確認。明確な炎上歴がなくても、企業の価値観と乖離した投稿があれば注意が必要です。
炎上の多くは「過去の掘り起こし」から始まるケースが多く、投稿時の文脈まで丁寧に読み取る視点が求められます。 - 起用可否を判断するための言動チェックリスト
企業のブランドイメージや業界特性に合わせて、NG項目を明文化したチェックリストを準備することが望ましいです。主観や曖昧な感覚に頼らず、組織として判断しやすい基準を作っておくことで、選定段階での判断ミスを防げます。 - 契約書へのモラル条項の明記
配信中・SNS上での不適切な発言が発覚した場合のペナルティや、発信前後の注意事項(NGワードや報告ルールなど)を契約に盛り込むことで、リスクに対する意識を高め、万が一の際にも適切に対応できます。
2.起用後の継続管理
配信者との契約後、実際にコンテンツが発信されていく段階での管理フェーズです。
このタイミングで「見ていなかった」「気づかなかった」となると、被害が拡大するリスクがあります。
- 定期的な言動チェックとフィードバック
配信者本人が気づいていないリスクの芽を、第三者視点で早期にキャッチ。配信後の振り返りや、炎上につながりかねない言動へのフィードバック体制があると、未然にトラブルを防げます。 - 問題発言を未然に防ぐための研修
企業側が望む言葉づかいやトーン、避けるべきテーマや言い回しを共有することで「知らなかった」が引き金になる炎上を減らします。配信者のプロ意識を育てる場としても有効です。 - 24時間365日の目視監視体制の導入
公式SNSのコメント欄や関連投稿を常時モニタリング。人の目で状況を読み取り、小さな火種の段階でアラートを出すことで、トラブルの回避につながります。
また、公式アカウント外のSNS投稿(一般ユーザーの言及など)もソーシャルリスニングで補完することで、さらに精度を高めることが可能です。
3.炎上発生時の対応体制
日頃からの備えと共に「起きたときにどう動けるか」がその後の評価を大きく左右します。
- ステートメント発表のテンプレート化
初動で企業がどう反応するかが、評価を大きく左右します。事実関係の整理、謝罪・説明・再発防止策の基本構成をあらかじめ準備しておき、初動8時間以内を目安に一次対応を出せる体制を整えましょう。 - 本人による謝罪のタイミングや言葉選びのポイント
当事者である配信者が謝罪する場合、単に「謝ればいい」では済みません。誤解を招かないよう、文脈や言葉選びに慎重さが求められます。企業側がサポートに入ることで、謝罪が逆炎上になるリスクも軽減されます。 - コミュニティの信頼回復のためのリブランディング戦略
一度傷ついたブランドを立て直すには、単発の謝罪ではなく、企業姿勢そのものの見直しが必要な場合もあります。キャンペーンやビジュアル変更などを通じて「変わった」ことを明確に伝え、再起のきっかけにします。
まとめ:信頼される関係づくりが、最強のリスク対策に
短期的なプロモーションで終わらず、信頼できる配信者と長く協力していく関係を築くことこそが、最も堅実で、リスクに強いインフルエンサー施策です。
- フォロワー数よりも価値観の相性を重視
影響力よりも、倫理観やブランド理解のある配信者が、結果として長く頼れる存在になります。 - チェックと振り返りを繰り返す仕組み化で質の向上へ
発信前後の気づきを共有し、次に活かす体制をつくることで、配信者と一緒に質を高めていけます。 - 育てる関係性が長期的な武器に
一過性のPRにとどまらず、継続的なコミュニケーションを通じて、企業の価値観を自然に浸透させていくことが可能です。
アディッシュでは、24時間体制の目視監視とソーシャルリスニングを通じて、企業のリスク対策と安心をサポートしています。
・「そもそも規約をどう作ればいいかわからない」
・「投稿の監視が追いつかず、判断に困っている」
・「自社で体制をつくるのが難しい」
このようなお悩みがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

関連するお役立ち資料