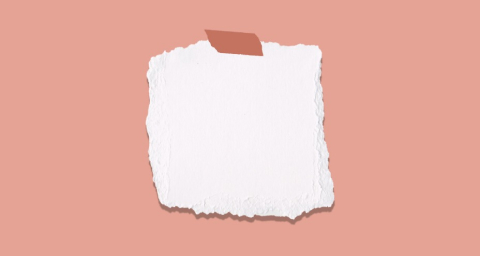はじめに:企業が直面するリスク
SNSやオンラインコミュニティ等の、企業がコントロールできない場所で、ブランドが語られることが多くなってきています。X(旧Twitter)、Instagram、TikTok、LINEオープンチャット──これらのプラットフォーム上では、日々多くのユーザーが企業や商品に対する意見を発信しています。
一つの投稿が、ブランドの信頼を一瞬で揺るがす。そんな時代において、「何か起きたら対応する」では遅すぎるのです。企業価値を守るためには、炎上や批判の“兆候”を早期に察知し、先手を打つ体制=モニタリングの仕組みが必要不可欠です。

関連するお役立ち資料
企業が押さえるべきSNS危機管理
1. リスクとは何か?企業が理解すべき“リスク”の構造
「リスク」と聞くと、多くの人は「悪いことが起こる可能性」と捉えるかもしれません。しかし、リスクマネジメントの国際基準であるISO 31000では、リスクは「不確実性の影響」と定義されています。つまり、企業が掲げる目標に対して、どのような不確実性が影響を与えるか、という視点です。
SNS時代における企業リスク、特に“ソーシャルリスク”は以下のように整理できます。
① 外部からの火種
顧客やユーザーからの批判投稿、商品不満、従業員対応へのクレームなど
例)「対応の悪い店員がいた」という投稿が拡散され、ブランドイメージが低下する。
② 内部からの火種
従業員による情報漏洩、不適切投稿、コンプライアンス違反の告発
例)従業員がSNSに社外秘情報を誤って投稿し、批判が殺到する。
③ 自社プラットフォーム上の火種
企業が運営するコミュニティでのトラブル、レビュー荒らしなど
例)企業公式コミュニティで不正行為や荒らしが発生し、収拾がつかなくなる。
SNSの特徴は、火種が発生すると即座に拡散するという点にあります。トラブルの芽は、静かに広がり、大きなクレームや信頼失墜につながる可能性を秘めています。
▼関連記事
炎上リスクとは?炎上の危険性から対策方法までをわかりやすく解説
2. 企業がとるべきリスク対応策とその選択肢
企業が直面するリスクに対処する方法はさまざまですが、リスクマネジメントの基本に立ち返ると、対応策は大きく4つの種類に分類されます。自社の状況に応じて、以下の選択肢を組み合わせ最適な戦略を取ることが重要です。
- リスク回避
リスクを伴う活動自体を中止・排除し、リスクそのものをなくす対応策。
例)SNS炎上リスクが高いテーマのキャンペーン自体を見送る。 - リスク低減
リスクの発生確率や影響度を抑えるための対策を講じる。
例)SNS運用ポリシー策定や社員研修により、不適切投稿の発生を抑制する。 - リスク移転
リスクによる損失負担を他者に移す方法
例)風評被害対策の専門会社に監視業務を委託する、あるいはリスク保険に加入する。 - リスク受容
発生可能性や影響が小さいリスクについて、あえて受け入れる選択。
例)SNS上の軽微な批判や一時的なクレームは許容し、大事に至らぬよう経過観察する。
いずれの対応策を講じるにしても、まず前提となるのは「自社を取り巻くリスクの把握と評価」です。
最初に、想定されるリスクを洗い出し、それぞれの発生確率と影響度によって優先順位を付ける必要があります。
そのうえで、「どのリスクに、どの対応を当てはめるか」を検討していきます。
たとえば、SNS上の炎上リスクに対しては、次のような対策が考えられます。
- 発生を予防するための施策(例:社内ルールの整備や、社員への教育によるリスクの低減)
- 発生後の被害を最小限に抑える施策(例:初動対応の迅速化=リスク低減、専門業者への委託=リスク移転)
すべてのリスクを完全にゼロにすることは困難です。
しかし、複数の対応策を組み合わせることで、リスクを「想定内」に管理することができます。それが、リスクマネジメントの本質であり、企業活動を安定させるための重要な考え方です。
▼関連記事
炎上リスクとは?炎上の危険性から対策方法までをわかりやすく解説
3. なぜ“モニタリング”が今必要なのか
SNSは“秒単位”で情報が拡散するため、炎上リスクが高まっている
企業活動とSNSは切り離せないものになった今、ユーザーの一投稿がわずか数分で炎上に発展するケースも珍しくありません。実際、誤解や感情的な反応が一気に拡散され、企業側が気づく頃には「手遅れ」になっている事例も多く見られます。
こうした背景のもと、SNS上の火種を“いち早く察知する”ことは、リスク対策の初動において極めて重要です。情報の拡散スピードが桁違いの現代では、リアルタイムに異常を検知できる体制がなければ、企業の信用や売上に深刻な影響が及ぶ可能性があります。
通報や問い合わせでは“初動”に間に合わない
従来のように、顧客からの問い合わせやクレームを受けてから対応する方法では、現在のSNSリスクへの初動としては不十分です。炎上の兆候は必ずしも企業に直接届くわけではなく、関係のない第三者の投稿から広がることもあります。
そのため、「通報を待つ」「話題になるまで気づかない」といった受け身の体制では、早期対応が間に合わず、結果的にブランド毀損や不買運動につながるリスクが高まります。能動的なモニタリング体制が、迅速な初動を可能にする唯一の方法です。
表に出ない不満が突然のクレーム・解約につながる
SNS上には明確なクレームだけでなく、ユーザーがつぶやいた軽微な不満や違和感が数多く存在しています。こうした“声にならない兆候”が放置されることで不信感が蓄積し、ある日突然、解約や批判の投稿につながることもあります。
企業がこうした兆候を見逃さず、日常的にモニタリングし対策に生かしていくことで、大きな炎上や顧客離れを未然に防ぐことが可能になります。モニタリングは、単なるリスク対策ではなく、企業への信頼を高めるための“攻めの施策”としても有効です。
▼関連記事
炎上の構造から考えるSNSの炎上対策とは
4. モニタリングとソーシャルリスニングの違いとは?
SNS上の投稿を把握・活用する方法として、「モニタリング」と「ソーシャルリスニング」があります。一見似たような活動に見えますが、目的・視点・活用タイミングが異なります。両者の違いを整理すると、以下のとおりです。
|
項目 |
モニタリング |
ソーシャルリスニング |
|
目的 |
自社・ブランドに関する投稿の監視と即時対応(炎上予防、顧客対応) |
顧客の声や市場の傾向を分析し、戦略に活かす(商品企画、広告施策など) |
|
注目する情報 |
「何を言われているか」=個別投稿をリアルタイムに把握 |
「なぜそう言われているか」=投稿群から背景や傾向を読み解く |
|
反応スピード |
即時性が重要(リアルタイムで察知・対処) |
長期的視点での分析(週次・月次で集計・分析) |
|
代表的な活用シーン |
炎上対応、クレーム初動対応、ブランド保護 |
市場調査、顧客インサイトの発見、キャンペーン効果測定 |
|
企業における役割 |
リスク管理・守りの姿勢 |
戦略立案・攻めの姿勢 |
両者は「守り」と「攻め」の関係にあり、役割の異なるものを相互に補完し合う存在です。
たとえばモニタリングによってネガティブ投稿を早期に発見・対処し信頼を守りつつ、ソーシャルリスニングによって顧客の本音やニーズを把握し、より良い商品・サービスづくりへとつなげる。こうした好循環が、企業のSNS活用を進化させる鍵となります。
5. モニタリングが必要とされるリスクの具体例
SNSやコミュニティが企業活動と密接に結びつく現代において、さまざまなリスクが日々発生しています。こうしたリスクを通報が来る前に察知し、早期対応につなげられるのがモニタリングの強みです。ここでは、特に注意すべきリスクタイプとその具体例を紹介します。
|
投稿種別 |
想定リスク |
モニタリングの有効性 |
|
社会的配慮の不足投稿 |
「ジェンダー表現」に関する批判がXで拡散 |
拡散前に不適切表現を検知し、速やかな訂正・謝罪対応が可能 |
|
誹謗中傷 |
実名社員への連続批判投稿 |
個人名を含むネガティブ投稿を検知し、風評拡大を防ぐ |
|
虚偽レビュー |
意図的な★1レビューが急増 |
特定キーワードの急増を検知し、プラットフォーム通報につなげる |
|
不適切投稿(内部) |
コミュニティでの荒らし・差別投稿 |
速やかに削除・警告し、他ユーザーの離脱や炎上を防ぐ |
|
バイトテロ動画 |
店舗スタッフの迷惑行為が拡散 |
店名タグの投稿監視で早期社内対応と削除依頼が可能 |
|
情報漏洩・内部告発 |
社外秘の誤投稿がSNSに流出 |
「社名+流出」などで検索し、拡散前に初動対応を実施 |
|
なりすまし |
偽アカウントからの詐欺投稿 |
公式と異なるアカウントを発見し、通報・削除対応へ |
これらの事例からも明らかなように、モニタリングは「企業のリスクマネジメントの初動装置」として機能します。特に“初期の兆候”を見逃さず対応できるかどうかが、信用維持と損害回避の分かれ道となるのです。
▼関連資料
企業に迫るリスク50選 ~経営・広報・人事・法務が知るべきリスク~
6. モニタリングの対象と手法(SNS・コミュニティ・UGC)
企業が実際にどの範囲をどのようにモニタリングすべきかを考える際、ポイントとなるのは「監視対象(Where)」「検知方法(How)」「体制(Who)」の3つです。ここでは、メディアの種類別・方法別に整理して解説します。
対象別の概要
|
種別 |
主な対象 |
特徴 |
|
SNSモニタリング |
X(旧Twitter)、Instagram、TikTok、Facebook、YouTubeなど |
拡散性が高く、リアルタイム性も高いため炎上の初動発見に最適。ストーリーズや短尺動画など見逃しやすい投稿にも注意が必要。 |
|
コミュニティモニタリング |
LINEオープンチャット、Discord、自社運営の掲示板・ファンコミュニティなど |
ユーザー同士の対話が中心で、荒らし・差別発言・ルール違反などの管理が求められる。企業主導であるがゆえに“責任”も大きい。 |
|
レビュー/UGC監視 |
ECサイトのレビュー欄、Googleレビュー、UGC投稿(写真・動画) |
一見ポジティブに見える投稿にも風評リスクが含まれることもあり、評価・投稿内容を継続的にチェックする必要がある。 |
方法別比較(AI型・人力型・ハイブリッド型)
|
手法 |
特徴 |
注意点 |
|
AI型 |
SNS APIやクローリングにより自動で投稿収集・通知。広範囲かつ24時間対応が可能。 |
誤検知や文脈の誤解釈に注意。キーワード設計次第で精度が大きく変わる。 |
|
人力型 |
モニターが目視で投稿を確認。表現のニュアンスや感情も読み取れる。 |
コストと人員負担が大きい。 |
|
ハイブリッド型 |
ツールで絞り込んだ投稿を人が精査。効率と精度のバランスが良い。 |
どこに人手をかけるか(キーワード、感情分析など)設計が重要。 |
運用体制と社内プロセス
モニタリング体制の成功には「誰が」「どのようなプロセスで」行うかが鍵となります。自社内で広報・CS部門が兼務する場合、スピードと専門性の面で限界があります。そのため、以下のような対応が検討されます。
- 外部モニタリングサービスの活用:24時間365日対応、緊急時の対応支援、専門的なチューニングによるキーワード設定などが可能。
- 社内体制の強化:自社でノウハウを蓄積し、判断・対応力を持つ体制をつくることで将来的なインハウス化を目指すことも可能。
いずれの場合でも、モニタリングで発見されたリスクにどう対処するかの「エスカレーションルール」や「初動対応マニュアル」の整備が不可欠です。たとえば「重大な投稿を検知したら、1時間以内に対応会議を開催」といった明確なフローをあらかじめ設計し、訓練しておくことがリスク軽減に直結します。
7. モニタリング導入のステップと設計ポイント
企業がこれからモニタリング体制を構築・導入する際に押さえるべき基本ステップと設計上のポイントについて、以下の5段階で整理します。
- リスク定義(何が問題か)
まずは、モニタリングの目的と対象とするリスクを明確にします。誹謗中傷、炎上、虚偽情報、内部告発、なりすましなど、自社にとってどのような投稿が「対応すべき問題」となるのかを定義しておきましょう。これにより、対象投稿のスコープやアラート条件を明確にできます。 - 対象決定(チャネル・時間帯・範囲)
次に、監視対象を「どの媒体を、いつ、どのくらいの頻度で」行うかを決めます。たとえば、即時拡散力のあるX(旧Twitter)やInstagramは優先監視対象となります。深夜や休日も含めて常時対応すべきかどうかも、自社の業種やリスク特性に応じて判断しましょう。
・主要チャネル:X、Instagram、TikTok、5ちゃんねる、匿名掲示板、LINEオープン チャット、Googleレビュー、ECサイトの口コミ
・優先時間帯:投稿の多い平日夜間や土日、リリース直後など - 体制設計(誰が監視・判断・対応するか)
社内チーム(広報・CSなど)による対応か、外部専門会社への委託かを選択します。社内体制であれば緊急時の判断が速い反面、リソースが限られる場合があります。外注する場合は、一次対応や報告フローを明確にし、社内担当との連携体制を設計することが重要です。
・判断権限:どのレベルの投稿で誰が判断するのか明記
・報告ルート:緊急時のエスカレーション体制の整備
・運営方針の共有:投稿判断基準やトーンの統一など - 運用設計(アラート閾値・報告ルール・通報テンプレ)
アラートが出る基準や報告・対応ルールを具体化します。どのようなキーワードが検知対象となり、どのくらいの頻度で報告・対応が必要なのかを事前に設定します。
・アラート条件:自社名+「炎上」「まずい」などリスクワードの組み合わせ
・通報テンプレート:社内共有用に報告フォーマットを作成
・SNS初期対応例:10分以内に広報・CSに連絡、30分以内に対応方針を決定 - 改善活用(得られた情報をFAQ・運営方針に反映)
実際のモニタリングで得られた投稿傾向やユーザーの声は、CS対応の強化や商品改善、FAQの充実などに活用可能です。また、定期的にPDCAを回し、キーワード設定や報告フロー、体制を見直すことで精度と効率を高めていくことが重要です。
・FAQ・テンプレの見直し:問い合わせ内容を分析して改善
・炎上事例の教訓化:社内マニュアルや研修資料への反映
・ガイドラインの改訂:投稿ルールやコミュニティ規約の調整
ポイントまとめ:
- 「目的・範囲・手法・体制・改善策」の5軸で設計する
- リスク定義と体制構築が曖昧だと、いざという時に機能しない
- 検知→報告→対応→改善のループを常に意識する
モニタリングは、単なる“監視業務”ではなく、企業にとってのリスクマネジメントおよび顧客接点改善の起点です。リスクを可視化し、守りと攻めの両輪でブランド価値を守り育てていく仕組みとして設計しましょう。
8. モニタリングで危機を回避した企業事例
モニタリング体制が整っていたことで、実際にリスクを未然に察知し、企業価値を守ることができた成功事例を紹介します。
① 回転寿司チェーン「スシロー」の迷惑動画炎上対応
・事例内容:
2023年1月、岐阜・スシロー店内で客が湯飲みや醤油さし、寿司を舐める迷惑動画がSNSで拡散。株価にも一定の影響が出ました。
(参考:ITmedia NEWS「スシロー迷惑行為に非難殺到)
・モニタリングによる対応:
拡散開始直後の投稿を監視チームが即座に検知し、企業は謝罪声明を出し、店内設備の改善や警察への通報も発表 。
・成果:
SNS上のネガティブ拡散が収まり、リスク対策として衛生管理やアクリル板設置など具体的施策が評価され、ブランド信頼の回復につな がりました。
② 四国放送による誤投稿への即時対応
・事例内容:
四国放送の公式Twitterで、運用ミスにより不適切な内容(特定政党批判)が投稿され、炎上リスクが発生。
(参考:ITmedia NEWS「四国放送、公式Twitterの「中の人」懲戒解雇 公明党批判のツイート“誤爆”、個人アカウントと取り違え」)
・モニタリングによる対応:
モニタリング体制で即座に投稿を検知し、迅速に削除と謝罪文を公表。再発防止策も明示されました。
・成果:
ネガティブ拡散を最小限に抑え、透明かつ迅速な対応が「企業として責任ある姿勢」として評価されました。
このように、モニタリングは「リスクの芽を最小の段階で摘む」ことで、炎上や信頼低下を防ぎ、企業のブランド価値を守る役割を果たします。特に、キャンペーン・公式発信・ユーザー交流といった“動的な場面”では、投稿監視の有無が危機対応の成否を大きく左右します。
まとめ:“気づける体制”が企業価値を守る
SNS・コミュニティ時代のリスク対策には、「いち早く気づき、素早く動ける体制」が不可欠です。炎上や情報漏洩を完全に防ぐことは難しくても、兆候を早期に検知し適切に対応できれば、被害を最小限に抑えられます。
実際、多くの企業がモニタリングによってリスクを未然に察知し、ブランド価値を守っています。ただし、モニタリングは導入して終わりではなく、継続的な改善や社内への定着が重要です。
また、収集したユーザーの声をCS改善や商品開発に活かすことで、モニタリングは「守り」だけでなく企業成長の起点にもなります。
最も注意すべきは、“知らないうちに信頼を失っている”状態です。そのリスクを防ぐためにも、「気づける体制」を整え、企業のレジリエンスを高めていきましょう。
アディッシュは、10年以上にわたりオンラインコミュニティやSNSのモニタリングを通じて、企業のブランド価値を守る支援を行っています。
誹謗中傷や炎上への備え、ルール設計、投稿監視、ユーザー対応方針の整理など、数多くの課題に対応した実績とノウハウがあります。
・「そもそも規約をどう作ればいいかわからない」
・「投稿の監視が追いつかず、判断に困っている」
・「自社で体制をつくるのが難しい」
このようなお悩みがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

関連するお役立ち資料
企業が押さえるべきSNS危機管理